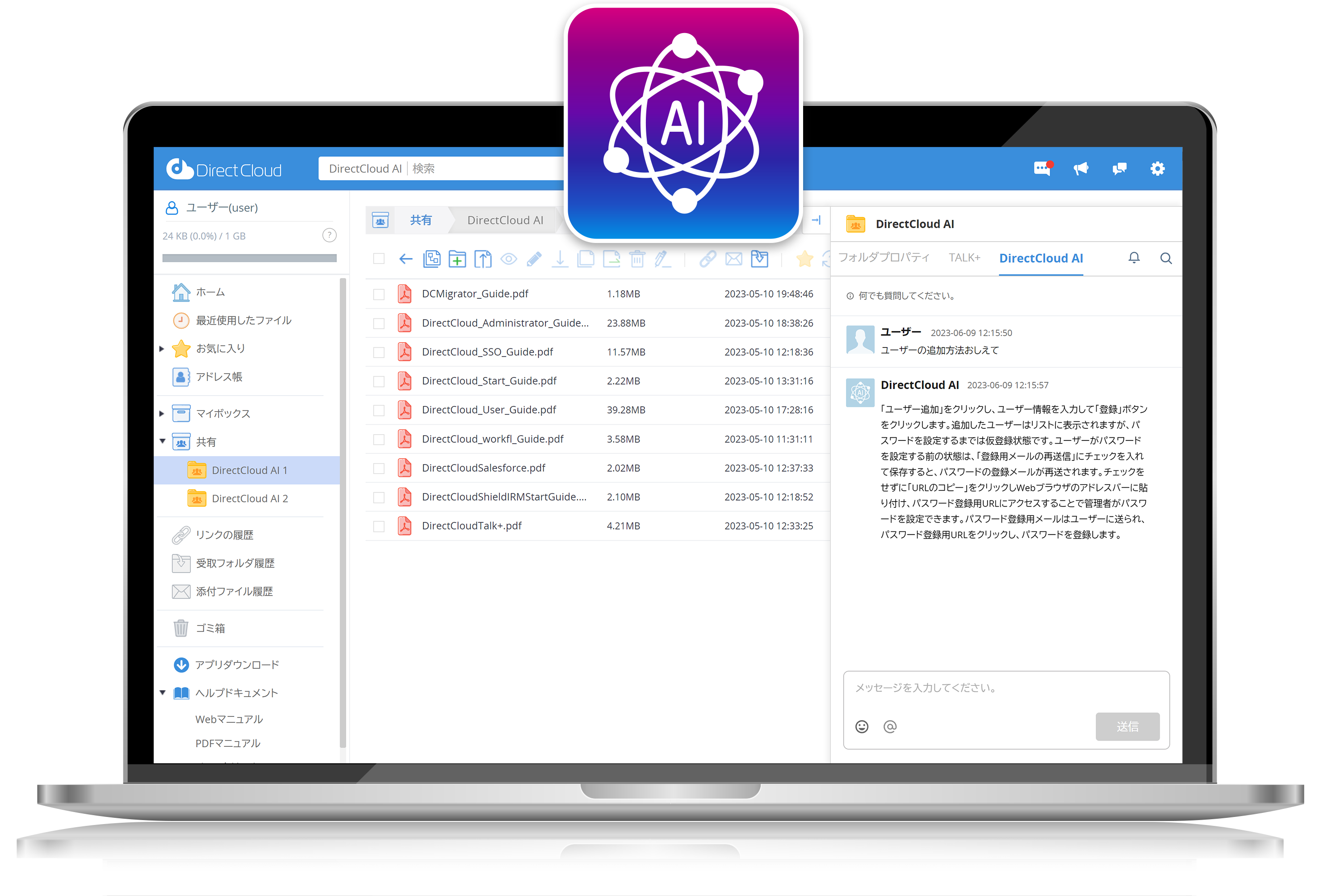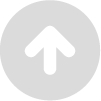生成AIを活用する企業・個人が増えている中で、生成AIを使いこなす人と、そうで無い人の格差が生まれ始めています。
あなたが、AIに使われる側ではなく、AIを使う側であるために、AIと上手く対話する方法について解説していきます。
- ●生成AIは入力された指示をもとに応答を生成します。そのためプロンプトはAIの性能を引き出す“鍵”となります。
- ●生産性を上げるためには、最初から目的に近い結果を得る必要があります。良いプロンプトは「やり直しコスト」を大幅に削減します。
- ●生成AIができる事は質問応答だけではありません。プロンプトを工夫することで、AIとの会話やアイデア出し、構成設計など“多機能アシスタント”として機能します。
 目次
目次- 1. 生成AIとプロンプトの基本理解
- 2. より良いプロンプトの作り方
- 3. プロンプトテクニックの活用例
- 4. セキュリティとリスク対策
- 5. まとめ
1. ⽣成AIとプロンプトの基本理解
近年、AIとの対話が日常的に利用されるようになってきました。その中でよく耳にする「プロンプト」という言葉。これは、生成AIに対する“指示”のことであり、AIとのコミュニケーション手段となるものです。
生成AIとは
生成AI(Generative AI)とは、人間のように文章や画像などを自動で作り出す人工知能のことです。たとえば、質問に答えたり、文章を要約したり、イラストを描いたりできます。ChatGPTやCopilotなどが代表例で、入力された言葉(プロンプト)をもとに自然なアウトプットを生成します。専門知識がなくても使えるため、仕事や日常生活のさまざまな場面で活用が広がっています。
2022年11月にOpenAI社からChatGPTがリリースされ、世界中に生成AIが広まりました。一過性のブームでは終わらず、現在も日々進化して利用範囲が拡大されています。
自然言語で指示できるのがプロンプトの魅力
従来のプログラミングでは専門的なコードを書く必要がありましたが、生成AIは「プロンプト」と呼ばれる“自然言語”でAIに指示を出すことができます。つまり、私たちが普段使っている言葉・言語(日本語)でAIにお願いができるのです。このような対話が実現できるのは「大規模言語モデル(LLM)」という技術によって、AIが膨大なテキストデータを学習し、人間の言葉を理解できるようになったためです。
ただし、自然言語だからといって、曖昧な表現ではAIは精度の高い応答を返せません。生成AIと良い対話をするためには少しテクニックが必要になるため、このコラムを最後まで読んでAIを活用できるようになってください。
プロンプトは“橋渡し役”のようなもの
「プロンプト」は、人間の言葉をAIが理解できるようにする“橋渡し”のような役割も果たします。自然言語で伝えられるとはいえ、人間同士の会話とは少し違い、AIには明確で構造的な指示が必要です。
基本は「1文1指示」。伝えたいことが複数ある場合は、箇条書きで整理するとAIがより正確に理解してくれます。詳細は次の章で解説していきます。
AIが理解しやすいプロンプトを書くために
プロンプトには、押さえておきたい「4つの要素」があります。これらを意識することで、AIとのコミュニケーションが格段にスムーズになります。
- 1. 目的:何をしてほしいのか
- 2. 対象:誰・何に対してなのか
- 3. 条件:どんな制約やルールがあるのか
- 4. 形式:どんな形で結果を出してほしいのか
これらを明確にすることで、AIはより的確な応答を返してくれるようになります。
2. より良いプロンプトの作り方
AIとの対話をより効果的にするためには、プロンプトの書き方を工夫することが重要です。前の章で紹介した「プロンプト4つの要素(目的・対象・条件・形式)」を意識することで、AIに伝えたいことがブレず、期待に近い回答を得ることができます。
この章では、ワンポイントテクニックと、定型化されたプロンプトテクニック集について紹介します。
プロンプトで使えるワンポイントテクニック
プロンプトの書き方にはいくつかのポイントがあります。
-
① 役割指定(ロール指定)
AIに役割を与えて、回答の視点やトーンをコントロール。
例:あなたはプロの編集者です。次の文章を校正してください。 -
② 出力形式を指定
箇条書き、表、JSONなど、欲しい形式を明示。
例:3つのアイデアを箇条書きで出してください。 -
③ 制約条件を追加
文字数、トーン、対象読者などを指定。
例:200文字以内の優しい口調で、初心者向けに説明してください。 -
④ ステップバイステップ指示
複雑なタスクは手順を分けて指示。
例:まず概要を説明し、その後に詳細な手順を示してください。 -
⑤ 例示
望む出力の例えを提示。
例:次の例のように回答してください: Q: ○○とは? A: ○○は… -
⑥ 思考の連鎖を促す
理由や根拠を求める。
例:結論に至るまでの理由を3ステップで説明してください。
これら複数のワンポイントテクニックを組み合わせてプロンプトを作成すると以下のようになります。
あなたはAIの専門家です。生成AI初心者向けに、500文字以内で生成AIの歴史について説明してください。その後、年表を箇条書きにしてください。
4つの要素「目的・対象・条件・形式」も含まれているのが分かるかと思います。
代表的なプロンプトテクニック
初心者としては上記の数あるワンポイントテクニックを毎回意識するのは大変かもしれません。そこで、生成AIにより良い応答をしてもらうための定型化されたテクニックが世の中に数多く存在しています。
「プロンプトテクニック」としてどの様なものが存在しているか。また、その特徴を知ることで、あなたも実践的なプロンプトがすぐに書けるようになります。
| # | プロンプトテクニック名 | 特徴 |
| 1 | Zero-Shot Prompting(ゼロショット) | シンプルで⼿軽。⽂脈や参考情報などは⼀切与えず、端的な質問をする⼿法です。出⼒の精度や⼀貫性は不安定な場合もあります。(使⽤⽅法は次章参照) |
| 2 | RGC Prompting(アールジーシー) | 明確に要素(Role, Result, Goal, Context, Constraint)を⽰し区分けすることで、AIの応答精度を⾼める構造化されたプロンプト⼿法です。出⼒の⼀貫性と品質が向上します。(使⽤⽅法は次章参照) |
| 3 | Goal-Seek Prompting(ゴールシーク) | ⼀度の指⽰でゴールを⽬指さず、AI側から質問をしてもらい、AI⾃らがプロンプトを作成・ブラッシュアップしていく⼿法です。 プロンプトに何を与えたら良いか分からない場合に利⽤できる強い味⽅です。(使⽤⽅法は次章参照) |
| 4 | Generated Knowledge Prompting(ジェネレーテッドナレッジ︓知識⽣成) |
AI⾃⾝に必要な知識を⽣成させてから質問に答えさせるプロンプト⼿法です。特に、外部知識が必要な質問や、モデルの内部知識だけでは不⼗分な場合に有効です。
[プロンプトテンプレート]
あなたは質問に答える前に、必要な知識を生成してください。
フォーマット: 1. 必要な知識を箇条書きで3〜5個書く 2. その知識を使って質問に答える 質問: {ここに質問を書く} |
| 5 | Chain-of-Thought (CoT) Prompting(チェーンオブソート) |
モデルに「途中の推論過程」を明⽰的に書かせることで、複雑な問題を正確に解くための⼿法です。特に、数学、論理推論、マルチステップの質問に強いです。
[プロンプトテンプレート]
質問に答える前に、ステップごとに推論を説明してください。
最後に「最終的な答えは〇〇です」と書いてください。 質問: {ここに質問を書く} |
| 6 | ReAct Prompting(リアクト) |
ReAct Promptingは「Reasoning(推論)」と「Acting(⾏動)」を組み合わせて、AIに「考えながら⾏動させる」ためのプロンプト設計⼿法です。特に、複雑なタスクや外部ツールの利⽤が必要な場合に有効です。 ただし処理時間やコストが⾼くなる傾向にあります。そのため、シンプルな質問にはオーバースペックになりやすいです。 [プロンプトテンプレート]
あなたは、与えられた質問に答えるために、次のフォーマットで推論と行動を繰り返してください。
フォーマット: Thought: 次に何をすべきか考える Action: 実行するアクション(例: Search[クエリ]) Observation: アクションの結果 …(必要に応じて繰り返す) Final Answer: 最終的な答え 質問: {ここに質問を書く} |
| 7 | 深津式プロンプト(ふかつしき) | 基本的な構成を考慮して⽣成AIの仕組みにあったインプットを与える考え⽅です。(使⽤⽅法は書籍「ChatGPTを使い尽くす︕深津式プロンプト読本」をご確認ください) |
| 8 | Multimodal CoT Prompting(マルチモーダル) | テキストと画像など複数のモダリティを組み合わせて、推論過程を明⽰的に書かせる⼿法です。通常のCoTを拡張し、画像認識や視覚情報を含むタスクで精度を⾼めます。 |
| #1 | |
| プロンプトテクニック名 | |
| Zero-Shot Prompting(ゼロショット) | |
| 特徴 | |
| シンプルで⼿軽。⽂脈や参考情報などは⼀切与えず、端的な質問をする⼿法です。出⼒の精度や⼀貫性は不安定な場合もあります。(使⽤⽅法は次章参照) | |
| #2 | |
| プロンプトテクニック名 | |
| RGC Prompting(アールジーシー) | |
| 特徴 | |
| 明確に要素(Role, Result, Goal, Context, Constraint)を⽰し区分けすることで、AIの応答精度を⾼める構造化されたプロンプト⼿法です。出⼒の⼀貫性と品質が向上します。(使⽤⽅法は次章参照) | |
| #3 | |
| プロンプトテクニック名 | |
| Goal-Seek Prompting(ゴールシーク) | |
| 特徴 | |
| ⼀度の指⽰でゴールを⽬指さず、AI側から質問をしてもらい、AI⾃らがプロンプトを作成・ブラッシュアップしていく⼿法です。 プロンプトに何を与えたら良いか分からない場合に利⽤できる強い味⽅です。(使⽤⽅法は次章参照) | |
| #4 | |
| プロンプトテクニック名 | |
| Generated Knowledge Prompting (ジェネレーテッドナレッジ︓知識⽣成) |
|
| 特徴 | |
|
AI⾃⾝に必要な知識を⽣成させてから質問に答えさせるプロンプト⼿法です。特に、外部知識が必要な質問や、モデルの内部知識だけでは不⼗分な場合に有効です。
[プロンプトテンプレート]
あなたは質問に答える前に、必要な知識を生成してください。
フォーマット: 1. 必要な知識を箇条書きで3〜5 個書く 2. その知識を使って質問に答える 質問: {ここに質問を書く} |
|
| #5 | |
| プロンプトテクニック名 | |
| Chain-of-Thought (CoT) Prompting (チェーンオブソート) |
|
| 特徴 | |
|
モデルに「途中の推論過程」を明⽰的に書かせることで、複雑な問題を正確に解くための⼿法です。特に、数学、論理推論、マルチステップの質問に強いです。
[プロンプトテンプレート]
質問に答える前に、ステップごとに推論を説明してください。
最後に「最終的な答えは〇〇です」と書いてください。 質問: {ここに質問を書く} |
|
| #6 | |
| プロンプトテクニック名 | |
| ReAct Prompting(リアクト) | |
| 特徴 | |
|
ReAct Promptingは「Reasoning(推論)」と「Acting(⾏動)」を組み合わせて、AIに「考えながら⾏動させる」ためのプロンプト設計⼿法です。
特に、複雑なタスクや外部ツールの利⽤が必要な場合に有効です。 ただし処理時間やコストが⾼くなる傾向にあります。そのため、シンプルな質問にはオーバースペックになりやすいです。 [プロンプトテンプレート]
あなたは、与えられた質問に答えるために、次のフォーマットで推論と行動を繰り返してください。
フォーマット: Thought: 次に何をすべきか考える Action: 実行するアクション(例: Search[クエリ]) Observation: アクションの結果 …(必要に応じて繰り返す) Final Answer: 最終的な答え 質問: {ここに質問を書く} |
|
| #7 | |
| プロンプトテクニック名 | |
| 深津式プロンプト(ふかつしき) | |
| 特徴 | |
| 基本的な構成を考慮して⽣成AIの仕組みにあったインプットを与える考え⽅です。(使⽤⽅法は書籍「ChatGPTを使い尽くす︕深津式プロンプト読本」をご確認ください) | |
| #8 | |
| プロンプトテクニック名 | |
| Multimodal CoT Prompting (マルチモーダル) |
|
| 特徴 | |
| テキストと画像など複数のモダリティを組み合わせて、推論過程を明⽰的に書かせる⼿法です。通常のCoTを拡張し、画像認識や視覚情報を含むタスクで精度を⾼めます。 | |
3. プロンプトテクニックの活用例
実際に、プロンプトテクニックを利用して生成AIに問いかけてみましょう。
ここでは、先に挙げた8つのテクニックから抜粋して実践的なプロンプトを3つ紹介します。
Zero-Shot Prompting で一般的な調べごとをサクッと実施
AIに対して事前に情報を与えずに指示を出す手法をZero-Shot Promptingと呼びます。
これは、簡単に調べごとをする時に利用します。Web検索するのと同様な手軽さで一番よく利用されています。ただし、プロンプトは曖昧な表現にならないようにし、欲しい情報に辿りつくような質問をするように心がけてください。
日本について教えて
日本の伝統文化を3つ挙げて、それぞれ50文字以内で説明を箇条書きにして
- ・茶道:抹茶を点てて客をもてなす礼儀作法の芸道。
- ・歌舞伎:化粧と衣装が特徴の伝統的な舞台芸術。
- ・折り紙:紙を折って形を作る日本独自の遊び文化。
Zero-Shot Prompting で社内勉強会に利用する資料を簡単に作成する
部分的に資料作成を依頼することができます。調べごとと文書作成まで一括で実施できるため、数分で資料が完成します。
下記は、プロンプト作成から応答が返ってくるまで2分程度でできたものです。
あなたはAIの専門家です。生成AI初心者向けに、500文字以内で生成AIの歴史について説明してください。その後、年表を箇条書きにしてください。
生成AIの歴史は、AI研究の進化とともに発展してきました。1950年代にAIの概念が誕生し、1980年代にはニューラルネットワークが注目されました。2000年代に入り、計算能力とデータ量の増加によりディープラーニングが進化。2014年にはGAN(敵対的生成ネットワーク)が登場し、画像生成が飛躍的に進歩しました。2020年代には大規模言語モデル(GPTシリーズなど)が登場し、自然言語生成やマルチモーダルAIが実用化され、生成AIはビジネスや日常に広く浸透しています。
年表
- • 1950年代:AIの概念誕生(チューリングテスト提案)
- • 1980年代:ニューラルネットワーク再注目
- • 2006年:ディープラーニングのブレイクスルー
- • 2014年:GAN(敵対的生成ネットワーク)発表
- • 2018年:GPT-1登場、大規模言語モデルの時代へ
- • 2020年:GPT-3登場、自然言語生成が実用レベルに
- • 2022年:ChatGPT公開、生成AIが一般利用に拡大
- • 2023年以降:マルチモーダルAIや生成AIのビジネス活用が加速
RGC Prompting で人事・総務の生産性アップ
RGC PromptingのRGCは下記単語の頭文字になります。
- ●Role (役割)
- ●Result (依頼)
- ●Goal (目的)
- ●Context (状況)
- ●Constraint (制約条件)
これらをMarkdown形式の見出し記号である半角のハッシュ “#” を用いてそれぞれ記載することで、求める情報に辿りつきやすくなります。
日本語で質問する場合には、上記の項目も日本語で記載すると良い結果が得られるようです。
「Context」は「状況」を表しますが、日本語では「詳細情報」とした方が、人間が理解しやすくなり内容を書きやすくなります。
- #役割
- #依頼
- #目的
- #詳細情報
- #制約条件
それでは、実例で見ていきましょう。
人事部が社内へのお知らせ文を作成する場面です。
-
#役割
あなたは、人事部長です。 -
#依頼
年次有給休暇を年間5日間取得していない方に向けて、取得を促す社内向けのお知らせ文を作成してください。
お知らせを掲示する際のタイトルも考えてください。 -
#目的
法律で定められたところにより、年間5日間の年休取得が会社側に義務づけられています。違法とならないように、従業員には適時年休を取得してもらう必要があります。 -
#詳細情報
対象は総合職の全従業員。
12月末日までに5日間の年休を取得して欲しい。
仕事が忙しくて休めないという意見もあるため、そのような従業員にも配慮した内容にする。
お知らせの掲載は9月1日とする。
お知らせの出元は人事部とする。 -
#制約条件
400文字以内にする。
前後の挨拶文は不要。
派遣社員、業務委託者は今回のお知らせの対象外とする。
-
掲示タイトル:
年次有給休暇の取得促進について(総合職対象) -
本文:
人事部より、総合職の皆様へお知らせです。年次有給休暇の取得状況を確認した結果、年間5日未満の取得者が確認されました。
法令により、会社は従業員に年5日の取得を義務づけられています。12月末までに5日間の取得をお願いいたします。業務の繁忙を考慮し、計画的な取得を推奨します。
作成したプロンプトよりも回答文の方が短くなっているので、生産性アップしているのか疑うかもしれません。
おそらく、慣れていない方がお知らせを作成した場合、いろいろな条件を盛り込んでとても長い分かりにくい文章になることが想像できます。
このタイトルと短い本文の中で、伝えたいことが的確に表されているため、数百人・数千人に伝えるには有用なお知らせが短時間で作成できたのではないでしょうか。
Goal-Seek Promptingでマーケティングの生産性アップ
Goal-Seek Promptingは、AI側から質問をして貰って、プロンプトをAI自らがゴールに向かって作成していく手法です。
この手法を利用すると、そもそもの「プロンプトを作る」部分をAIが一緒にサポートして考えてくれます。そのため、なにを生成AIに頼んだら良いか分からない方でも良いプロンプトが作成できて、的確な指示を出せるようになります。結果として、あなたのニーズに応える内容が得られます。
あなたには「プロンプト作成アシスタント」です。
目的は、私のニーズに最適なプロンプトを一緒に作り上げることです。このプロンプトは、あなた自身(AI)が利用します。
以下の手順で進めてください。
手順
#最初のステップ
最初に「どのようなテーマのプロンプトを作りたいか」を私に質問してください。私が答えた後、次の手順に進みます。
#私の回答に基づいて、下記3つのセクションを提示してください
- * 改良版プロンプト
私の入力をもとに、わかりやすく簡潔で、AIが理解しやすい形に書き直したプロンプトを提示してください。 - * 改善のための提案
プロンプトの精度を高めるために、どのような情報を追加すべきか提案してください。 - * 質問
プロンプトを改善するために、私から追加で必要な情報があれば質問してください。
#反復プロセス
私が追加情報を提供し、あなたが「改良版プロンプト」を更新する、というやり取りを繰り返し最終的に完成させます。
どのようなテーマのプロンプトを作りたいですか?
(例:ブログ記事の執筆、マーケティングコピーの作成、プログラミングコード生成、データ分析、アイデアブレインストーミングなど)
自由に教えてください!
「生成AIのプロンプトテクニック初級編」ウェビナーのレジュメを作りたい
ありがとうございます!テーマは「生成AIのプロンプトテクニック初級編」ウェビナーのレジュメですね。では、以下の3つのセクションを提示します。
✅ 改良版プロンプト
「生成AIのプロンプトテクニック初級編」ウェビナー用のレジュメを作成してください。
条件は以下の通りです:
- • 対象読者:IT知識がゼロ〜少しある初心者
- • 内容:10分で読めて、30分でハンズオンできる分量
- • ハンズオンは文章生成に特化
- • 文体:ビジネスライクだが堅すぎない
- • 最後に次回記事の案内とDirectCloud AIランディングページへの誘導を含める
✅ 改善のための提案
プロンプトをさらに精度高くするために、以下の情報を追加すると良いです:
- 1. レジュメの構成(例:イントロ、基礎知識、実践、まとめ)を指定するか?
- 2. 具体的なハンズオンのテーマ(例:「ブログ記事のタイトル生成」「メール文面作成」など)を決めるか?
- 3. トーンやスタイルの詳細(例:図解を入れる?箇条書き多め?)を明記するか?
- 4. ページ数や文字数の目安を設定するか?
- 5. 次回記事のテーマ案を含めるか?
✅ 質問
- • レジュメの章立てはどのようにしますか?(例:1. はじめに、2. プロンプトとは、3. ハンズオン、4. まとめ)
- • ハンズオンの具体的な題材は何にしますか?
- • 図やサンプルプロンプトを含めますか?
- • 全体の分量(文字数やページ数)はどれくらいを想定しますか?
次に、これらの質問に答えていただければ、さらに精度の高いプロンプトを作成できます。
👉 章立てやハンズオンテーマ、分量のイメージを教えていただけますか?
レジュメの章立てはどのようにしますか?
自己紹介、プロンプトとは、プロンプト手法の種類、まとめ
ハンズオンの具体的な題材は何にしますか?
世の中に存在しているプロンプト手法をいくつか紹介したい
図やサンプルプロンプトを含めますか?
図は要りません。サンプルプロンプトは欲しいです。
全体の分量(文字数やページ数)はどれくらいを想定しますか?
本編40分、質疑応答10分、計50分でできる文量にしてください。
このように、AIからの提案を受け、質問に答えながらプロンプトをブラッシュアップしていきます。
〜 やり取りが長くなるので中略 〜
ありがとうございます!すべての条件を反映して、最終版のプロンプトを作成しました。
✅ 完成版プロンプト
「生成AIのプロンプトテクニック初級編」ウェビナー用のレジュメを作成してください。条件は以下の通りです:
• 対象読者:IT知識ゼロ〜少しある初心者
• 章立て:
- 1. 自己紹介
- 2. プロンプトとは
- 3. プロンプト手法の種類(以下を含む)
- o Zero-Shot Prompting
- o RGC Prompting
- o Goal-Seek Prompting
- o Few-Shot Prompting
- o Chain-of-Thought
- o Role-Playing
- o Persona Prompting
- o Instruction-based Prompting
- o Self-Consistency
- o ReAct
- o Tree-of-Thought
- 15. まとめ(次回記事の案内+DirectCloud AIランディングページ概要スライド)
• ハンズオン:実施しない。手法紹介のみ。
• サンプルプロンプト:各手法に対して
- o 入力例(複数行可)
- o 出力例(複数行、実際の内容は後で追記するので枠だけ)
• 図:不要(ただしDirectCloud AI紹介スライドには図を含める)
• 文体:ビジネスライクだが堅すぎない
• 分量:本編40分+質疑応答10分で説明できる程度(10分で読める内容)
✅ DirectCloud AI スライド仕様
• 構成:
- o サービス概要(1〜2文)
- o 主な特徴(箇条書き3〜4点)
- o 「詳しくはこちら」+URL
• デザイン:テキスト+シンプルな図(サービスロゴやイメージ)
✅ 次のアクション
このプロンプトを使って、
① レジュメのドラフト(章立て+各手法の説明+サンプルプロンプト枠)
② DirectCloud AI紹介スライドのテキスト案を生成します。
上記のプロンプトを使って、レジュメを3階層までの章立てのみでテキスト出力してください。
生成AIのプロンプトテクニック初級編 – ウェビナーレジュメ
1. 自己紹介
• 氏名・所属・担当領域
• 今日のゴール
- o 初心者が「安全に」「再現性を持って」文章生成プロンプトを使えるようになる
2. プロンプトとは
• プロンプトの定義と役割
• 良いプロンプトと悪いプロンプトの例
• 設計の基本原則
- o 目的(Goal)を明確にする
- o 対象(Context)を記載する
- o 制約条件(Constraints)を指定する
- o 出力形式を定義する
3. プロンプト手法の種類
以下の11種類を紹介し、それぞれに「概要」「入力例」「出力例(枠のみ)」を記載。
- • Zero-Shot Prompting
例示なしでタスクを直接指示する最もシンプルな方法 - • RGC Prompting(Role/Goal/Constraints)
役割・目的・制約を明示して期待値を揃える - • Goal-Seek Prompting
望ましい最終アウトプットから逆算して必要な情報を導く - • Few-Shot Prompting
良い例を2〜3個与え、パターン学習を促す - • Chain-of-Thought
推論の手順を明示的に書かせ、正確性を高める - • Role-Playing
AIに役割を与えて、視点や口調を変える - • Persona Prompting
読者像を具体化して適切な難易度と表現に調整 - • Instruction-based Prompting
指示と評価基準を明記し、出力品質を管理 - • Self-Consistency
複数の思考経路で案を生成し、多数決または統合で安定解に近づける - • ReAct
思考(Reason)と行動(Act)を交互に促すフォーマット - • Tree-of-Thought
複数の分岐(仮説)を並行して展開・評価し、最良ルートを選ぶ
4. まとめ
• 本日の要点
- o 目的・前提・制約・出力形式を明確にする
- o 手法を使い分けて精度と再現性を高める
- o 「反復して磨く」ことが最強のプロンプト技法
• 次回予告
- o 中級編:ツール連携(ReAct実践)、評価フレーム(ルーブリック化)、ガードレール設計
• DirectCloud AIのご紹介
- o 詳細は概要スライドをご参照ください
Goal-Seek Prompting は、AIとのやり取りがとても長くなりますが、AIが同僚のように一緒に考えてくれるので、一人で煮詰まらずに業務が進められるプロンプトテクニックです。
4. セキュリティとリスク対策
多くの生成AIツールが世の中に出てきています。テキストの質問・回答だけでなく、資料の作成や画像生成、動画生成など多岐にわたります。
最近では、入力された内容を学習しない・再利用しないと利用規約などで謳われている生成AIも少なくありません。
しかし、そのツールの提供元がハッキリしないとか、知らない企業が運営しているなど、心配になることがあると思います。
そこで、そのような生成AIを利用する場合に気を付けるべき事項について挙げていきます。
プロンプトに含めない方が良いとされる情報
次の一覧は、生成AIに限らず、あらゆる場面で取り扱いに気を付けるべき内容ですが、これらは、個人向けにサービス提供をされているような生成AIについても同様です。
| 情報の種類 | 具体例 | 理由 |
| 個人情報 | 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、マイナンバー | 個人情報漏えいのリスクがあるため。AIサービスや通信経路で第三者に渡る可能性がある。 |
| 認証情報 | パスワード、APIキー、トークン、 暗証番号 |
不正アクセスやアカウント乗っ取りの原因になるため。AIは安全な保管場所ではない。 |
| 機密業務情報 | 社内プロジェクト名、未公開製品情報、 契約内容 |
外部に流出すると企業の信用失墜や法的リスクが発生するため。 |
| 財務情報 | 銀行口座番号、クレジットカード番号、 決算データ |
金銭的被害や不正利用のリスクがあるため。 |
| 医療・健康情報 | 病歴、診断結果、処方箋 | 個人のセンシティブ情報であり、プライバシー侵害や法令違反につながる恐れがある。 |
| 顧客・取引先情報 | 顧客リスト、取引条件、契約書 | 顧客との信頼関係を損ない、法的問題を引き起こす可能性があるため。 |
| 内部システム情報 | サーバー構成、ネットワーク図、 ソースコード |
サイバー攻撃や不正利用のリスクが高まるため。 |
| 個人情報 | |
| 具体例 | 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、マイナンバー |
| 理由 | 個人情報漏えいのリスクがあるため。AIサービスや通信経路で第三者に渡る可能性がある。 |
| 認証情報 | |
| 具体例 | パスワード、APIキー、トークン、暗証番号 |
| 理由 | 不正アクセスやアカウント乗っ取りの原因になるため。AIは安全な保管場所ではない。 |
| 機密業務情報 | |
| 具体例 | 社内プロジェクト名、未公開製品情報、契約内容 |
| 理由 | 外部に流出すると企業の信用失墜や法的リスクが発生するため。 |
| 財務情報 | |
| 具体例 | 銀行口座番号、クレジットカード番号、決算データ |
| 理由 | 金銭的被害や不正利用のリスクがあるため。 |
| 医療・健康情報 | |
| 具体例 | 病歴、診断結果、処方箋 |
| 理由 | 個人のセンシティブ情報であり、プライバシー侵害や法令違反につながる恐れがある。 |
| 顧客・取引先情報 | |
| 具体例 | 顧客リスト、取引条件、契約書 |
| 理由 | 顧客との信頼関係を損ない、法的問題を引き起こす可能性があるため。 |
| 内部システム情報 | |
| 具体例 | サーバー構成、ネットワーク図、ソースコード |
| 理由 | サイバー攻撃や不正利用のリスクが高まるため。 |
リスクと対策
生成AIを利用する上で以下のような注意すべき点が挙げられます。
★印を付けた項目については、RAG対応の企業向け生成AIサービスを社内利用することで、対策を取ることが考えられます。
- • 個人情報や機密情報が外部サーバーに保存され、第三者に漏れる可能性。
- • 対策:
- • 個人情報・機密情報をプロンプトに含めない。
- • 匿名化やダミーデータを使用。
- • 利用サービスのプライバシーポリシーを確認。
- • 悪意ある入力により、AIが意図しない情報を開示するリスク。
- • 対策:
- • 最低限の入力制限を設ける。
- • 個人任せにせず、組織単位でAI運用ガイドラインを策定。
- • 社員へのセキュリティ教育を実施。
- • チェック体制を構築し、事故発生時の対応フローを事前に準備。
- • AIが事実と異なる情報を生成し、誤った意思決定につながる。
- • 対策:
- • 重要情報は必ず信頼できるソースで検証。
- • AIの回答をそのまま業務判断に使わない。
- • AI生成物に第三者の著作物が含まれる可能性や、法令違反のリスク。
- • 対策:
- • 商用利用時は利用規約を確認。
- • 個人情報保護法やGDPRに準拠した運用。
- • 人間だけでの監視には限界がある。
- • 対策:
- • 自動検知システムを導入し、ガイドライン違反の文言をフィルタリング。
- • 使用時にアラート通知を行う仕組みを構築。
5.まとめ
生成AIを味方にするために
プロンプトについて、基礎的なことをこのコラムでは学んできました。
あなたが望まなくとも、すでに生成AIと共存する時代に突入しています。AIを便利に利用して、生産性を上げる、楽をする、自分の知識・能力を超えた業務をこなしていきましょう。
最後に、生成AI入門者のあなたへ「プロンプト活用の5つの指針」を示します。行動の方向性として持っていていただければ幸いです。
プロンプト活用の5つの指針
-
① プロンプトは“橋渡し役”である
プロンプトは単なる指示文ではありません。あなたの知恵や意図をAIに正しく伝える“橋渡し役”であり、課題や目的をAIが理解できる形にするツールです。良いプロンプトによって、AIの力を最大限に引き出せます。
-
② 繰り返し改善を
何も考えずに使うと生成AIは本来の力を発揮できません。プロンプトを繰り返し改善することが、最適なアウトプットへの近道です。
-
③ 改善志向の人こそ武器になる
プロンプトは自律的改善を加速させる強力なツールです。小さな一歩から始め、試行錯誤すると結果がすぐに現れます。良いプロンプトは社内に共有し、全社的なスキルアップと業務効率改善につなげましょう。
-
④ コミュニケーション力がカギ
生成AIを業務で利用する方は、人から要望を正確に聞き出し、AIにわかりやすく伝えるディレクション力とコミュニケーション力が求められます。これは、AI時代の新しい必須スキルです。人との対話が苦手な人でもAIとなら仲良く話せるかもしれません。
-
⑤ AIは“パートナー”、試行錯誤を楽しみましょう
AIは人間の代替ではなく補完です。人間の判断力とAIの生成力を組み合わせ、試行錯誤を楽しみながら最適解を導くことが、生成AIを“味方”にする最大のポイントです。